公開日:2025.10.20
📘 本記事は連載シリーズ「介護者のための明日が少し楽になるヒント(資格取得編)」の最終回です。
▶ 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編
▶ 第2回:ついに申込!資料だけじゃ分からなかったリアル ― 申込編
▶ 第3回:申込後でも体験会へ参加して大正解! ― 体験会編
▶ 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編
▶ 第5回:知識が“本物のスキル”に変わった瞬間 ― 実技教習・検定試験編(前編:1日目)
▶ 第6回:視覚障害者の手引きとロールプレイ ― 実技教習・検定試験編(後編:2日目)
▶ 第7回(この記事):資格取得後に生きる力に変わった「支える」という視点 ― 総括編
プロローグ
資格を取ることが目的ではなく、学びを「生きる力」に変えること。
サービス介助士の学びを通して、私は“支える”という言葉の意味を見つめ直しました。
この総括編では、今までの6回の学びの記録を振り返りながら、資格を通じて変わった視点と、これからの生き方についてお伝えします。
第1章:サービス介助士の学びが“自己変容”へ導いた瞬間
合格証書(サービス介助士認定状:2025年9月9日付け)が届いた日のことを、今でもはっきり覚えています。
喜びというより、静かな感謝の気持ちが湧き上がってきました。
この半年間を振り返ると、私は“資格を取るために学んだ”というより、“自分を見つめ直す旅”をしていたのだと感じます。
最初の目的は、妻の介護のためでした。
「正しい介助の知識を学び、少しでも安全に支えたい」――それが始まりでした。
(第1回:動機編 参照)
けれど、講座を通して学んだのは、それだけではありません。
介助とは、相手のためだけでなく、自分の心と向き合うことでもある。
“誰かを支える”とは、“自分も変わっていく”ということでした。
第2章:感情だけでは届かない「思いやりの技術」
最も印象に残っているのは、実技教習(第5回)での車いす介助の体験です。
力任せに押すと、車いすが思うように動かない。
段差の手前で一度止まり、角度を確かめ、相手の安全を確認しながら進む。
頭では分かっていたことが、体で理解できた瞬間でした。
高齢者疑似体験では、視界を覆われ、耳元で響く音や段差の振動に、想像以上の不安を感じました。
それは、これまで介助される側の視点を持てていなかった自分への気づきでもありました。
“思いやり”は感情だけでは届かない。知識と技術があってこそ、安心を届けられる。
それを身をもって学んだ時間でした。
第3章:支えることで自分も変わる ― 日常の変化
妻の車いすを押すとき、以前よりも一歩後ろで呼吸を合わせるようになりました。
「押す」ではなく、「一緒に進む」という感覚です。
段差の前では、「一段上がりますよ」と声をかける。
そのわずかな言葉のやり取りが、互いの心を落ち着かせます。
介助は“助けること”ではなく、“その人が自分らしくいられるよう支えること”。
そう思えるようになってから、介護の時間が穏やかになりました。
まだ機会はないのですが、街で困っている人を見かけても、もう迷わず声をかけられる。
第6回で学んだ視覚障害者の手引きやロールプレイでの経験が、実践へのハードルを下げてくれました。
職場でも、部下や同僚の表情をよく見るようになりました。
相手のペースに寄り添う姿勢――それが、日常の中に根づいていったのです。
第4章:知識を「実践」と「発信」に循環させる
サービス介助士資格の勉強を始める前、私はよく“先回り”していました。
妻が迷わないように、こちらで決めて、こちらで動く。
それが思いやりだと信じていたのです。
けれど今思えば、その“親切”が、妻から「選ぶ力」を奪っていたのかもしれません。
自宅学習を経て、講義や体験を重ねる中で、私の中の「介助=代行」という考え方は、少しずつ変わっていきました。
本当に必要なのは、情報を伝え、相手が自分で選べるように支えること。
それが「安全」と「尊厳」を両立させる介助なのだと気づいたのです。
そして、この気づきを記録しようと、私はブログを始めました。
ブログを始めたのには理由があります。
これからサービス介助士を目指そうと考えている方に、私のリアルな体験を伝えたい。
そして、「一緒に学び、支え合いながら、より良い介護を目指していける場所をつくりたい」と思ったのです。
記事を書くたびに、学びが自分の中で整理され、
「誰かの役に立てるかもしれない」という気持ちが、私のモチベーションになっていきました。
資格取得後、行動は確実に変わりました。
一時帰宅の際は、先回りをやめて、まず「どうしたいですか?」と尋ねるようになりました。
外出時の車いす介助では、段差の前で「上がりますね/下りますね」と声をかけ、安心を確認してから動く。
こうした小さな積み重ねが、妻の表情をやわらげ、私自身の介助にも余裕を生みました。
家庭の中だけでなく、街で困っている人を見かけたときも、自然と声をかけられるようになりました。
学びを活かすとは、自分の中に閉じ込めないこと。
書き、実践し、分かち合う――その循環の中で、「学び」は「生きる力」に変わっていきます。
それこそが、サービス介助士の資格が私に教えてくれた、一番大切なことです。
そして今、私は思います。
この学びを「資格」で終わらせず、“生き方”として続けていくことこそが、次の一歩なのだと。
――次章では、これから挑戦するあなたへ、私からのメッセージをお届けします。
第5章:学びを“行動”へ ― あなたの第一歩を応援
もし今、「興味はあるけれど、自分にできるだろうか」と迷っているなら、
どうかその気持ちのまま立ち止まらずに、一歩を踏み出してみてください。
大切なのは、“完璧にできること”ではなく、“やってみようと思える気持ち”です。
その小さな一歩が、介助を学ぶ道のはじまりになります。
学ぶ過程で迷ったり、壁にぶつかったりするかもしれません。
けれど、そのひとつひとつの迷いや不安の中にこそ、
「思いやりを形にする力」が育っていくのだと、私は身をもって感じました。
Q. 学んで良かったことは?
A. 「助ける」から「共に考える」へと視点が変わりました。
相手の立場を想像し、安心を届ける力が身につきました。
その気づきが、家庭でも職場でも、私自身の生き方をやさしく変えてくれました。
Q. 大変だったことは?
A. 実技教習では、“できない自分”に何度も向き合いました。
でも、その悔しさがあったからこそ、学びの一つひとつが心に残っています。
(第5回実技編①、第6回実技編② 参照)
Q. どんな人に向いている?
A. 家族介護をしている方、福祉・接客の仕事をしている方、
そして“人の気持ちに寄り添いたい”と感じているすべての方に。
思いやりを感覚だけでなく、技術として学びたい人には、きっと大きな価値があります。
Q. 一言メッセージを
A. 優しさは、技術で支えられてこそ届く。
支えたいと思うその気持ちが、もう“始まり”です。
合格証書を受け取ったとき、私はようやくスタート地点に立ったと感じました。
この資格は、終わりではなく、“思いやりを実践する旅”の入り口です。
もしあなたが迷っているなら、まずは無料体験会(第3回:体験編参照)を覗いてみてください。
実際に講師の話を聞くだけでも、「自分にもできるかもしれない」と感じられるはずです。
どうかあなたも、自分のペースで一歩を踏み出してください。
その学びが、きっとあなた自身をやさしく変えてくれるはずです。――私がそうだったように。
エピローグ:「思いやりを形にする」次のステージへ
この連載を通して、私は「支える」という言葉の意味を何度も考え直しました。
介護も、接客も、家庭の中のふれあいも――すべては“人と人との関係づくり”です。
サービス介助士として学んだ知識と技術は、日常のあらゆる場面で生きています。
それは、相手を尊重し、安心を届けるという生き方そのものだと感じます。
もしこの記事が、これから学びを始める方の背中を、ほんの少しでも押せたなら。
それが、私にとってこの資格を取った意味なのだと思います。
「思いやり」は、あなたの中にもすでにあります。あとは、その優しさを形に変えるだけです。
🌱 ここから始めませんか?
この記事を読んで「私も挑戦してみたい」と感じた方へ。
次のステップを参考に、学びの第一歩を踏み出してみてください。
📍 STEP1:まずは資格の全体像を知る
📍 STEP2:申込前に知っておきたいポイント
📍 STEP3:無料体験会に参加してみる
▶ 第3回:体験会レポート|参加して分かった3つの価値
▶ 📝 無料体験会の申込はこちら(公式サイト)
📍 STEP4:学習の進め方を確認する
📍 STEP5:実技教習のイメージをつかむ
▶ 第5回:実技教習1日目|車椅子介助と高齢者疑似体験
▶ 第6回:実技教習2日目|検定試験までの流れ
🌸最後に…一緒に「サービス介助士」を目指しませんか?(PR)
この記事を読んで、「私もサービス介助士に挑戦してみたい!」と感じてくださった方がいらっしゃれば、これほど嬉しいことはありません。
今が一歩を踏み出すタイミングです。
この連載で紹介した学びが、あなたの日常を、そして誰かの安心を支える力になりますように。

※当リンクはアフィリエイトプログラムに参加しています。詳細をご確認の上、お申し込みください。
SPECIAL THANKS: 「おもてなし」の心と「安全」の技術を学ぶ
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 公式サイトはこちら


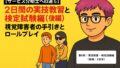
コメント