日々の介護に追われていると、どうしても目の前のことに精一杯になりがちです。日々の声かけ、食事の準備、薬の投与、体調管理…。しかし、介護生活が長くなるにつれて、私たちは身体的なケアとはまた別の、非常に大きな問題に直面することがあります。
それが、「お金」と「法律」の問題です。
こんにちは。ブログ管理人のみっちゃんです。 このブログでは、私が介護に関するブログを作成するにいたる体験を綴る「プロフィール」や、私がサービス介助士などの資格取得を通して「介護を学ぶ」過程を綴っています。それは、妻の介護、そして自分自身の心の平穏のために、私が必要だと感じたからに他なりません。
しかし、今回、このブログに新しいカテゴリを設けることにいたしました。
なぜなら、私自身が今、妻の遺産分割調停という、大きな法律問題の渦中にいるからです。
介護保険制度や医療費のこと、そして、もしもの時の成年後見制度や相続のこと。これらは、決して他人事ではなく、介護生活と地続きにある、避けては通れない道です。
専門家に相談しても、公的な窓口を訪ねても、明確な答えが見つからずに途方に暮れる夜がありました。その孤独と不安の大きさは、実際に当事者になってみて初めて分かるものでした。
だからこそ、私は自身のリアルな体験を記録し、発信することを決めました。この新しいカテゴリ『介護とお金・法律』は、そうした私の決意の証です。
このカテゴリで扱うテーマについて
このカテゴリでは、私が実際に直面し、悩み、調べ、行動したことを中心に、以下のようなテーマについて綴っていく予定です。
- 成年後見制度は本当に必要? 私がなぜこの制度の利用をためらっているのか、その理由と背景にあるデータについてお話しします。
- 「特別代理人」という選択肢 成年後見に代わる一つの可能性として、私が現在進めている「特別代理人」の選任について、そのリアルな過程を記録します。
- 【実録】弁護士の探し方 どこに相談すれば良いのか分からない…そんな八方塞がりの状態から、私がどのようにして弁護士を探しているのか、その具体的なステップを共有します。
- 遺産分割調停のリアルな流れ 今後、調停が進んでいく中で、当事者として何を感じ、どう対応していくのかを正直にレポートします。
- 介護にかかる費用と使える公的制度 日々の介護生活で実際に必要となるお金や、負担を軽減するために知っておきたい制度について、改めて整理します。
これらの記事は、私の状況が進むにつれて、一つずつ追加していく予定です。
記事をお読みいただく上での、私からのお約束
ここで、一つだけお伝えしておきたいことがあります。 私は、法律の専門家ではありません。
ですから、このカテゴリの記事は、難しい法律用語を解説したり、法的な正解を示したりするものではありません。
そうではなく、一人の介護者、一人の当事者として、私が何に悩み、どう考え、どう行動したのか。そのリアルな過程と、その時々の感情を、ありのままに綴っていくことをお約束します。
私の失敗や遠回りが、この記事を読んでくださっているあなたの、何かを考えるきっかけや、次の一歩を踏み出すためのヒントになれば、と心から願っています。
最後に:一人で抱え込まず、この場所を「心の拠り所」に
介護生活は、時に私たちを社会から孤立させます。身体的な負担に加え、お金や法律といった専門的な問題が降りかかってくると、その心労は計り知れません。
もしあなたが今、同じように複雑な問題に一人で向き合い、不安な夜を過ごしているのなら、ぜひこの場所を思い出してください。
この場所が、同じように介護とお金の狭間で悩む人々にとって、情報を交換し、経験を分かち合い、そして「一人じゃないんだ」と感じられる「心の拠り所」の一つになれば、これほど嬉しいことはありません。
一緒に考え、学び、この困難な道を乗り越えていきましょう。
▼ あなたの経験も、お聞かせいただけませんか?
この問題は、一人で抱え込むにはあまりにも複雑で、心細いものです。もし、この記事を読んで何か感じることや、ご自身の似たようなご経験、あるいは「こんな制度もあるよ」といった情報があれば、ぜひ下のコメント欄で教えていただけると嬉しいです。
また、X(旧Twitter)でも日々の気づきやブログの更新情報などを発信しています。同じように悩む方々と繋がり、支え合える場にしていきたいと考えていますので、お気軽にフォローしてください。
[みっちゃん]https://x.com/kaigotips24
免責事項
本記事は筆者の経験と公開資料に基づいた一般情報であり、個別案件に対する法的アドバイスではありません。
具体的なご相談は弁護士など専門家へご確認ください。
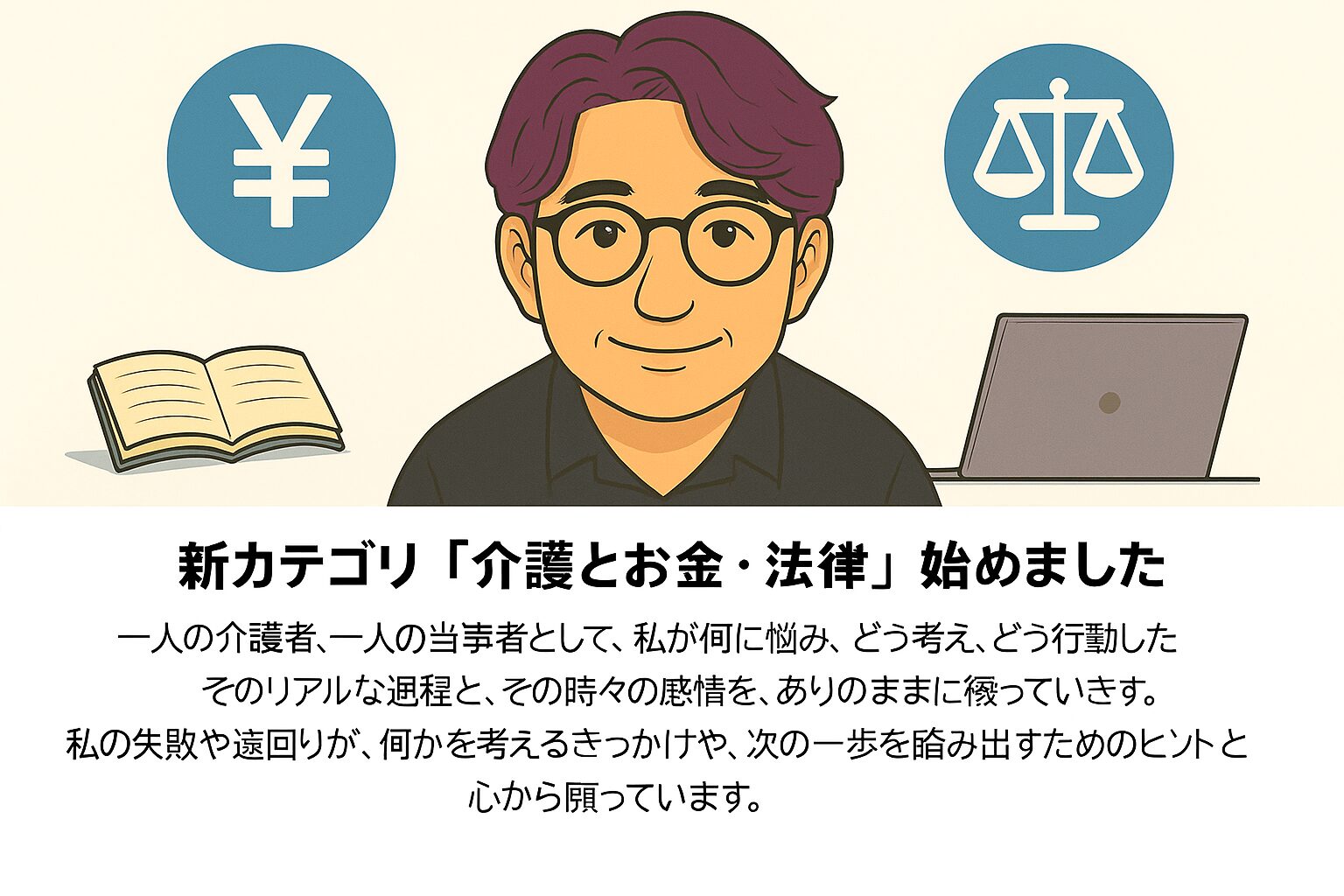



コメント