📘 この記事は連載シリーズ
「介護者のための明日が少し楽になるヒント」の一部です。
- ▶ 第1話:すべては突然の電話から始まった ― 介護生活の入口
- ▶ 第2話:知っているだけで救われる―介護生活が楽になる制度の話
- ▶ 第3話:介護生活に変化をもたらした介護支援専門員との出会い
- ▶ 第4話:見えない負担と向き合って ― 家族の変化が教えてくれたこと
- ▶ 第5話:家族の因縁と向き合って ― 母と娘に伝えたいこと
- ▶ 第6話:「安心」とは何かを問い続けた日々 ― 娘の独立と妻との向き合い(この記事)
導入:2021年以降の「現在地」― 変化する家族のかたち(過去の振り返りは今回で一区切り)
妻が高次脳機能障害を発症してから、早いもので20年以上が過ぎました。この連載では、第1話からこれまで、過去の出来事を時系列に沿って詳しくお話ししてきました。ここまで読んでくださった方、共感の声を寄せてくださった方に、心から感謝申し上げます。
今回をもって、過去の出来事をこのように詳細に振り返る形式は、一旦区切りとさせていただこうと思います。
今回の第6話では、もう少し時間を現在に近づけて、コロナ禍の2021年から今日に至るまでの出来事を中心にお話しします。この数年間で、次女が社会人として完全に独立し、私たち家族の形はまた大きく変化しました。そして、それは妻の介護のあり方、そして私自身の生き方にも、新たな問いを投げかけることになったのです。
介護の現実、時に立ちはだかる制度の壁、そして第5話でも触れた「終活」というテーマと、私はどのように向き合ってきたのか。過去を振り返る最後の章として、ありのままを綴っていきます。
1. 娘の独立、そして一人になった私に託されたもの
少し時間を遡りますが、私は2015年から3度にわたって心臓の冠動脈の施術(カテーテル治療)を受けました。正直、身体は限界を訴えていたのだと思います。それでも、当時は自分の療養よりも仕事を優先し、結果的に第4話で触れたように、家に残った次女に母(妻)のケアという重い負担を背負わせてしまっていました。
2017年、その次女が大学へ進学。私は費用のことも考え、自宅からの通学を望みましたが、娘の心は、もうこの家から離れたがっていたのかもしれません。そして、大学卒業後、彼女は地元を離れて社会人として完全に独立していきました。
娘が家を離れ、私と妻だけの生活、そして実質的には私の「ひとり介護」が視野に入ってきたその時、私はようやく、今後の妻の介護について真剣に考えざるを得なくなりました。
しかし、その過程は決して平坦ではありませんでした。かつて第3話で大変お世話になった元ケアマネジャーのWさんにも相談しましたが、そのやり取りの中で、私の仕事中心の生活や娘に頼ってきた経緯からか、「それは介護放棄ではないか」「(妻の)障害年金を自分の生活のために使っているのでは?」といった、非常に厳しい言葉を投げかけられる場面もありました。もちろん、Wさんなりのご心配からの言葉だったと理解しようと努めましたが、当時の私には深く突き刺さりました。
娘の独立は、同時に私の「ひとり暮らし」の始まりでもありました。そして、区役所の福祉課とも改めて話し合いを持つ中で、持病を抱える私一人での在宅介護は現実的に困難である、という判断に至りました。妻は一時的な滞在を目的とした短期入所施設(ショートステイ)を利用することに。ここから、妻にとって、そして私にとっても、「安心して穏やかに過ごせる場所」を探し求める日々が始まったのです。
2. 探し求めた「安心して穏やかに過ごせる場所」とは? ― 施設の現実
2021年4月、妻はショートステイを継続的に利用できる施設に入所しました。しかし、折しも新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化していた時期。面会は厳しく制限され、直接顔を見ることもままならない状況は、以前の施設利用とは全く異なるものでした。
「これで少しは安心できるだろうか…」そう思った矢先、現実は厳しいものでした。
- 2021年秋: 入所からわずか半年後、妻が施設内で転倒し骨折。リハビリが必要な状態に。
- 2022年2月: 施設内でクラスターが発生。妻も感染し、症状が悪化。コロナ中等症Ⅱと診断され、緊急入院。一時は人工呼吸器も検討されるなど、再び生死の境をさまようことに…。
幸い、コロナからは回復したものの、これらの出来事は妻の心身に大きな影響を与えました。そして2023年に入ると、施設での生活そのものに限界が見え始めてきました。
- 体力の低下は著しく、車椅子で過ごす時間が増えました。
- 服用していた薬の副作用により、急性膵炎を発症し、入退院を繰り返しました。
- 長年落ち着いていたてんかんの発作も再発するようになりました。
「安心・安全」であるはずの施設で、なぜこんなことが続くのか…。その言葉が、あまりにも空虚に響きました。一体、「安心」とは何なのか? 「安全」とは、誰の視点での安全なのか?
その間も、区役所との協議は続けましたが、「ご本人の状態を考えると、ご自宅での介護は困難です」という見解が繰り返されるばかり。施設での生活が難しくなっている現実があるのに、自宅にも戻れない…。私たち家族の「安心して穏やかに過ごしてほしい」という切実な願いは、制度の「正論」や「限界」の前に、行き場を失っていくように感じられました。
3. 制度の限界と、ようやく見つけた新たな光
追い打ちをかけるように、2023年1月、妻は薬の副作用による急性膵炎で入院。治療は成功したものの、この入院で身体機能はさらに低下してしまいました。そして、度重なる入退院や状態の変化を受け、それまで利用していた短期入所施設からは、ついに契約の継続が難しい、と打ち切られてしまったのです。
まさに八方塞がり。途方に暮れていた時、一つの可能性が示されました。それは、かつて妻の主治医だった先生が勤務する、地元の病院への転院でした。
幸運にも転院は叶い、慣れ親しんだ医師や環境のもとで、妻の病状は少しずつ回復に向かいました。そして、退院後の行き先として、自宅近くにある「地域移行支援施設」(※病院から地域生活へスムーズに移行するための支援を行う入所施設)への入所が決まったのです。ようやく、落ち着ける場所が見つかった… 心から安堵した瞬間でした。
今になって思えば、「もし、2021年の時点でこの施設への入所という選択肢があったなら、妻は骨折やコロナ感染、急性膵炎といった苦しみを経験せずに済んだのではないか…」そんな後悔にも似た感情が湧き上がってくることもあります。
でも、前回書いたように、これもまた、妻に与えられた「宿命」の一部だったのかもしれない、とも思うのです。起きてしまったことは変えられない。この現実を受け止め、妻が少しでも穏やかに過ごせるよう、これからの介護に改めて向き合っていこうと、今は考えています。
4. それでも私は生きる ― 終活という新たな出発点
娘たちはそれぞれの場所で自立し、妻は自宅からほど近い施設で、専門的なケアを受けながら静かに暮らしています。
20年以上にわたって私の肩に重くのしかかっていた「介護」という荷物を、少しだけ下ろすことができた今。私の日常は、自分自身の「終活」と、そして「孤独」と、静かに向き合う時間へとシフトしています。
心臓の基礎疾患を抱え、いつ何が起きるかわからない自分自身の身体。成人したとはいえ、娘たちの将来への漠然とした不安。そして、家族と離れて一人で暮らすことの、言いようのない寂しさ…。
決して平坦ではない現実の中で、それでも私は、このブログという場で、自分の言葉を紡ぎ続けています。それは、ただ過去を記録するためだけではありません。過去の経験と向き合い、未来への希望を繋ぎとめようとする、私なりの「生きる」ための営みなのかもしれません。
5. エピローグ:孤独の中で、それでも誰かとつながりたい(過去を振り返って)
この長い道のりを振り返り、多くの困難や葛藤、そして小さな希望を言葉にしてきました。その全てを通して、今、私が心から確信し、そして皆さんに伝えたいことは、この経験があったからこそ得られた実感です。
前回も書きましたが、私はもともと、人に頼ることがとても苦手な人間でした。「弱みを見せてはいけない」「自分で何とかしなければ」… そんな思い込みが、自分自身を、そして周りの人々をも苦しめていたのかもしれません。
この連載を通して、過去の出来事を一つ一つ言葉にしていく作業は、時に辛く、痛みを伴うものでしたが、同時に、自分自身の経験を客観的に見つめ直し、そこから得た教訓や想いを整理する、貴重な機会にもなりました。
このブログを通して自分の経験や想いを発信することで、今、私はようやく、その分厚い壁を少しずつ壊し、画面の向こうにいる「誰か」に、この思いを届けようとしています。
介護という長いトンネルを通り抜け、家族を見送り、そして一人になってみて… それでも、人生は続いていく。
このブログを読んでくださっている、あなたへ。
もしあなたが今、どんな形の孤独の中にいたとしても、どんなに先が見えないと感じていたとしても、どうか忘れないでください。
あなたは、決してひとりではありません。
この言葉が、ほんの少しでも、あなたの心の支えになることを願って。
今回で過去を振り返るお話は一区切りとなりますが、このブログはこれからも続けていきます。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
これまでの連載記事(過去の振り返り編)
- 【第1話】すべては突然の電話から始まった ― 介護生活の入口
- 【第2話】知っているだけで救われる―介護生活が楽になる制度の話
- 【第3話】介護生活に変化をもたらした介護支援専門員との出会い
- 【第4話】見えない負担と向き合って ― 家族の変化が教えてくれたこと
- 【第5話】家族の因縁と向き合って ― 母と娘に伝えたいこと
- ▶ 第6話:「安心」とは何かを問い続けた日々 ― 娘の独立と妻との向き合い(この記事)
💬 あなたの「安心」は何ですか?
今回の記事では、介護における「安心」について問いかけました。施設でのトラブルや制度の壁など、厳しい現実にも触れました。あなたが介護の中で感じる「安心」、あるいは「不安」は何でしょうか? もしよろしければ、コメント欄であなたの声を聞かせてください。
次回からは、また少し視点を変えて、介護生活の中で役立つ具体的な情報や、現在の心境などについて、お届けできればと考えています。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
🌱 最後まで“安心”に暮らすために、今できる準備を。
ひとりになった今、見えてきた「制度の限界」と「支えのかたち」。
これからの暮らしを考えるための情報をまとめました。
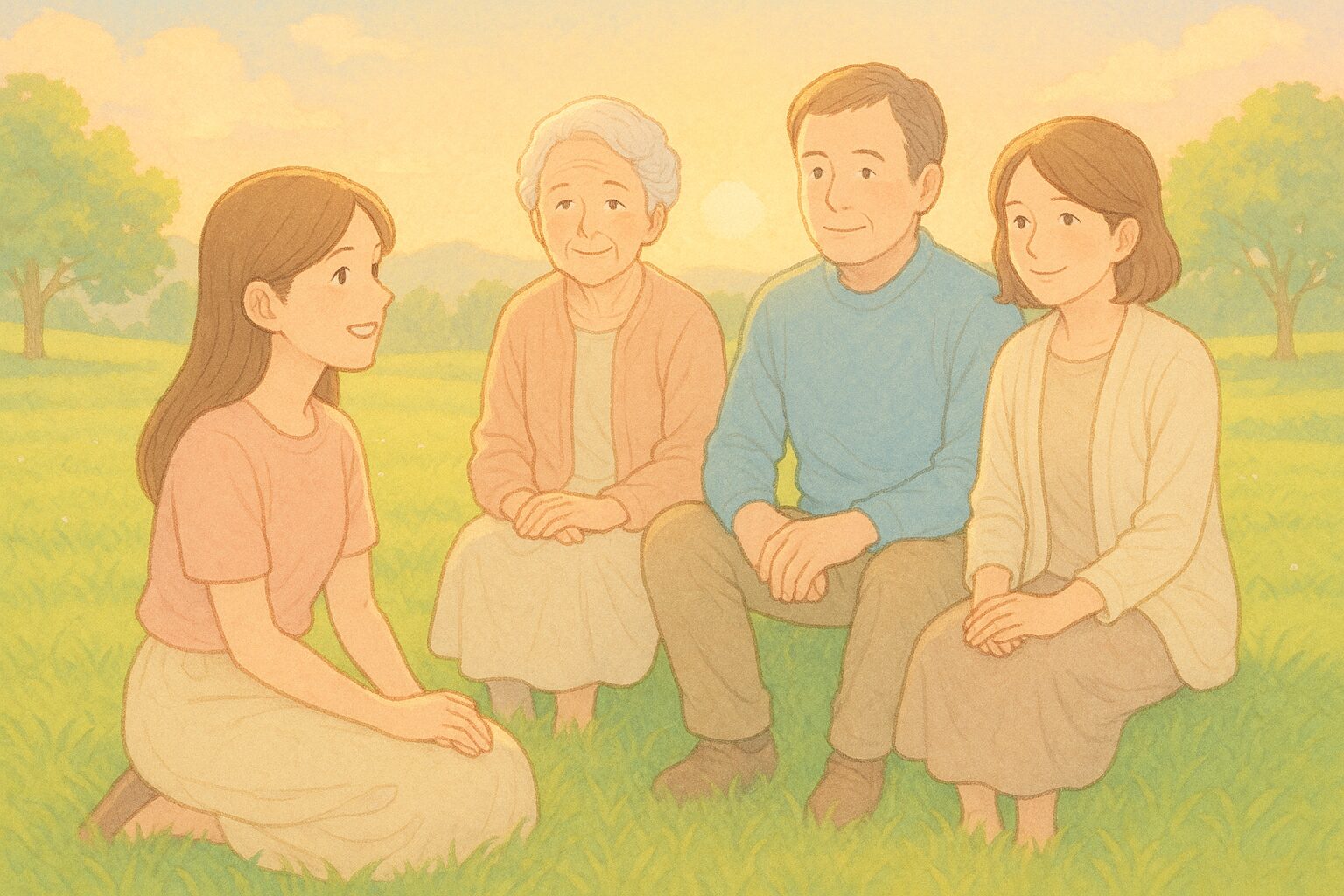


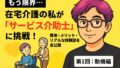
コメント