将来の在宅介護に限界を感じた筆者が民間資格「サービス介助士」取得に挑戦。資料請求だけでは分からなかった「本当の不安」と体験会の活用法とは? 申込前に知っておいてよかったこと、手続きの注意点も含めてリアルに紹介する連載の第2回〈申込編〉。
📘 この記事は連載シリーズ
「介護者のための明日が少し楽になるヒント(資格取得編)」の一部です
▶ 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編
▶ 第2回:(この記事):ついに申込!資料請求だけじゃ分からなかった「リアル」―申込編
▶ 第3回:申込後でも体験会へ参加して大正解! ― 体験会編
▶ 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編
▶ 第5回:知識が“本物のスキル”に変わった瞬間 ― 実技教習・検定試験編(前編:1日目)
▶ 第6回:視覚障害者の手引きとロールプレイ ― 実技教習・検定試験編(後編:2日目)
▶ 第7回:資格取得後に生きる力に変わった「支える」という視点 ― 総括編
妻の介護を通して「もっとできることがあるはず」と感じ、サービス介助士の資格取得を目指す日々の記録。
連載第2回目となる今回は、いよいよ 申込編 です。
前回の「動機編」では、私がなぜこの資格に挑戦しようと決意したのか、その経緯と思いをお伝えしました。今回は、資料請求から実際の申し込み手続き、さらに申し込み前に確認しておいて良かった点まで、体験をもとに詳しくご紹介します。
これから資格取得を考えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
第1章:公式サイトを読んで、決意を新たにした日
サービス介助士の資料請求は、思った以上にスムーズに進みました。
公式ホームページのコンタクトフォームから必要事項を記入して送信すると、間もなく返信メールが届き、記載されたURLからPDF形式の資料をダウンロードできる仕組みです。
資料はパンフレット形式で、講座の概要や他の資格との比較などが簡潔にまとめられていました。ただ、正直なところ、内容は最小限という印象で、「これだけで判断するのは少し難しいかもしれない…」と感じたのが本音です。
もう少し、実際に学んでいる方の声や、具体的なQ&Aといった、より詳細な情報が欲しいと思いました。そこで私は、改めてケアフィット共育機構の公式サイトをじっくりと読み込むことにしました。その中で出会ったのが、2016年に連載されていた「えみちゃんのサビ介とっちゃおうかな!?」という全14回のコラムでした。
👉 コラムはこちら
このコラムは、社会人1年目の「えみちゃん」が、仕事と勉強の両立に悩みながらも、ブラインドサッカーのボランティアに参加するなど様々な経験を重ね、翌年に合格を果たすまでの実体験が綴られていました。その内容は非常にリアルで、読んでいて私自身も励まされる思いがしました。特に、えみちゃんが「私にできるだろうか」という不安を抱えながらも、一つひとつの課題を乗り越えていく姿は印象的でした。
「若いえみちゃんがこれほど努力しているのだから、私にも、まだできることがあるのではないか」
そう思わせてくれる言葉がたくさんあり、気づけば時間を忘れて読み込んでいました。このコラムを読み終える頃には、サービス介助士への挑戦の意志が、より一層固まっていたのです。
第2章:体験会を申し込む前に、確認しておいてよかったこと
えみちゃんのコラムで勇気をもらった私は、サイトのメニューをもう一度丁寧に見直しました。すると、「無料講座体験会」という項目が目に留まりました。詳細を確認すると、自宅から通える範囲の東京での次回の開催は6月20日とのこと。また、オンラインでの無料講座説明会も用意されているようでした。
👉 体験会・説明会の情報はこちら
「まずはこの体験会に申し込んで、実際の雰囲気を感じてみよう」そう思った矢先、ある一文が私の注意を引きました。
参加者特典:「無料体験会・無料説明会(オンライン)参加後に講座へ申し込むと、合格後にバッジをプレゼント」

画像出典:公益財団法人日本ケアフィット共育機構
“特典”という言葉には、やはり少なからず心が動きます。そこで、ふと考えました。 「もし、先に講座本体へ申し込んでしまった場合、この特典は受けられないのだろうか?」
実は私自身、「思い立ったが吉日」と、体験会を待たずにできるだけ早く講座に申し込みたいという気持ちが強かったのです。しかし、特典があるのなら、それも考慮したいところです。
そこで、迷わずケアフィット共育機構にメールで問い合わせてみました。
すると、
「講座申込時の備考欄に『6月20日の体験会に参加します』と記入していただければ、特典の対象になります」
と、丁寧なご回答をいただきました。
この回答を聞いて、安堵しました。「それならば、今すぐ申し込んでも問題ない。むしろ、先に申し込みを済ませておけば、体験会当日はより集中して話を聞けるかもしれない」と考え、すぐに申込みのページへ進むことにしました。こうした事前の確認は、後々の安心感に繋がるものですね。
第3章:いよいよ本番!実際の申し込み手続きについて
実際の申し込み手続きは、思っていた以上にシンプルで、操作に不慣れな私でも戸惑うことなく進められました。
主な入力項目は以下の通りです:
【必須項目】
- 申込区分:クレジットカードや銀行振込などが選択できましたが、私は「振込」を選択しました。
- お支払方法:私は「振込」を選択(クレカも選べます)
- 氏名・フリガナ・ローマ字このローマ字表記が、合格後の認定証に記載されるとのことです。間違いのないよう、慎重に入力しました。
- 性別/生年月日/電話番号/住所/メールアドレス(非常に重要な項目です)/教材送付先
【任意項目】
- この資格をどこで知りましたか?:私は「知人から」と記入しました。
- コメント・備考:ここに「6月20日の体験会に参加します」と記入しました。
注意点
手続きの中で特に注意すべき点は、やはり「記入ミスをしないこと」だと感じました。 特にメールアドレスは重要です。万が一間違えてしまうと、申込完了の通知メールが届かず、不安な気持ちで過ごすことになりかねません。私は、念のため何度も確認しました。
全ての入力が完了すると確認画面が表示され、内容を最終チェックした後、「送信」ボタンを押して手続きは完了です。 後々のために、確認画面と完了画面のスクリーンショットを保存しておきました。これで、サービス介助士講座の申し込みは無事に完了です。数分後には「【サービス介助士資格取得講座】お申込みありがとうございます」というメールが無事届きました。大きなステップを一つ進められたように感じました。
第4章:申し込みを終えて、今思うこと
こうして正式に申し込みを終えた今、「ついにスタート地点に立ったのだな」という実感が胸に広がっています。まだ講座自体は始まっていませんが、この一歩を踏み出せたことが、ささやかながら自信にも繋がったように思います。新しい挑戦ですが、今は前向きな気持ちでいっぱいです。
次はいよいよ、6月20日の体験会です。 どのような話が聞けるのか、どのような体験ができるのか、今からとても楽しみにしています。
そして、このブログを読んでくださっている、同じように不安や期待を抱えている方々の何かの参考になれば…。そんな思いを込めて、次回は体験会当日の様子や、そこで私が感じたこと、学んだことについて、詳しくお伝えしたいと考えています。
次回予告:体験会のリアルレポートをお届けします!
いよいよ次回は、6月20日に参加したサービス介助士・無料体験会の様子を詳しくレポートする予定です。
- 実際の雰囲気ってどうなの?
- 参加して分かった“想像と違うこと”とは?
- 疑問が晴れて、受講の決意が深まった瞬間
介護に悩むあなたの背中をそっと押す内容になるよう、しっかりお届けします。
👉 次の記事公開のお知らせは、ぜひトップページからチェックしてください!
最後に…一緒に「サービス介助士」を目指しませんか?(PR)
この記事を読んで、「私もサービス介助士に挑戦してみたい!」と少しでも感じてくださった方がいらっしゃれば、これほど嬉しいことはありません。
下記のリンクから、私が申し込んだ「サービス介助士資格取得講座」の詳細をご確認いただけます。まずは情報収集の一環として、気軽にチェックしてみてはいかがでしょうか?
※当リンクはアフィリエイトプログラムに参加しています。詳細をご確認の上、お申し込みください。
ご確認の上、お申し込みください。



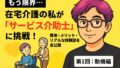

コメント