📘この記事は連載シリーズ「介護者のための明日が少し楽になるヒント(資格取得編)」の一部です
▶ 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編
▶ 第2回:ついに申込!資料請求だけじゃ分からなかった「リアル」―申込編
▶ 第3回(この記事):申込後でも体験会へ参加して大正解! ― 体験会編
▶ 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編
▶ 第5回:知識が“本物のスキル”に変わった瞬間 ― 実技教習・検定試験編(前編:1日目)
▶ 第6回:視覚障害者の手引きとロールプレイ ― 実技教習・検定試験編(後編:2日目)
▶ 第7回:資格取得後に生きる力に変わった「支える」という視点 ― 総括編
サービス介助士について、ホームページやテキストを読み込むなかで、試験の概要や資格の内容についてはある程度理解しているつもりでした。
その中で特に気になったのが「接遇」という言葉。調べてみると、単なる“接待”や“おもてなし”とは異なり、サービス介助士の学ぶ接遇とは、もっと本質的で深い意味があることに気づかされました。
それは、相手が高齢者であっても障害のある方であっても、“一人の人間として尊重し、心から向き合うこと”。
▶ 関連投稿はこちら:【おみっちゃん】X(旧Twitter)
けれど、どれだけ資料を読み知識を得たつもりでも、「実際にその場に立ったとき、私は本当に動けるのだろうか?」という不安は消えませんでした。
そんな私の迷いに“答え”をくれたのが、今回の無料体験会だったのです。
今回は、6月20日に参加した体験会の様子と、そこで得たリアルな学びをレポートとしてお届けします。 この経験が、あなたのサービス介助士受講の一歩を後押しするきっかけになれば嬉しいです。
第1章:体験会当日までの心境と準備
「受講申込後でも体験会に参加していいのかな…?」 そんな疑問を抱きながら、私は体験会に申し込みました。 体験会とは、これから受講を検討する人のための場。そう思い込んでいた私にとって、「もう申し込んでしまった自分が行ってもいいのだろうか」という戸惑いがあったのです。
けれど、自分の中で気持ちを整理し、「初めてこの資格に触れる人の視点で参加しよう」と切り替えました。 前日には日本ケアフィット共育機構から丁寧な案内メールが届き、持ち物や流れもスムーズに確認できたことで、安心して当日を迎えることができました。
第2章:当日の流れと会場の雰囲気

当日は受付開始の30分前に会場に到着。周囲を少し歩き、気持ちを落ち着かせてから受付を済ませました。
会場には、手引き体験用のスペース、資料の閲覧コーナー、講義スペースと3つのエリアがあり、全体的に落ち着いた雰囲気が漂っていました。 参加者は私を含めて4名。机の上には「サービス介助士の早わかりBOOK」、バッジプレゼント付き専用申込用紙やアンケートなどが個別に置かれていました。
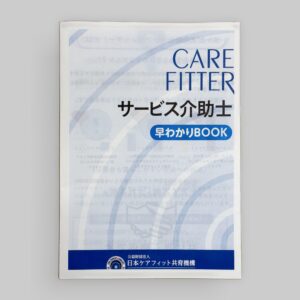
講師の方による自己紹介に続き、参加者一人ひとりの自己紹介へ。 職業も背景も異なる私たちでしたが、それぞれが「誰かのために学びたい」という共通点を持っていたことが印象に残りました。
講義では、障害者差別解消法の改正ポイントや日本の超高齢社会の現状に触れながら、サービス介助士の役割が語られました。 また、修了後の活動や、関連資格との違いについても丁寧に説明があり、学びの全体像をイメージすることができました。
資格取得の流れとして、提出した課題の合格後に行われる実技教習には2つのパターンがあるとのこと。①2日間連続の対面教習 ②オンライン講義+1日対面教習 私は、現場でしっかり教習を受けたいので、対面2日間を選ぶ予定です。
第3章:「思いやり」と「安全」の違いを体感した瞬間
体験会の中でも、特に印象的だったのが「手引き実習」でした。 参加者がペアになり、視覚障害者役と介助者役を交代で体験するロールプレイ。
まず講師の方が介助者となり、私は目を閉じたまま案内を受けました。 そのとき感じたのは、“見えない世界に身を置くこと”が、想像以上に不安だということ。 どんな段差があるのか、どんな椅子なのか分かっていても、「本当に大丈夫だろうか」と一歩踏み出すことにためらいを感じました。
反対に介助者として手引きを行った際には、声のかけ方一つで安心感が変わるということに気づかされました。 「今から左に曲がります」「前に上り1段の段差があります」「手前に椅子があります。お確かめになりますか」—— 普段なら意識しないことも、言葉にして丁寧に伝えることの大切さを実感しました。
このとき改めて気づかされたのは、段差や障壁が「障害」となっているのは、本人の身体ではなく環境との関係性によって生じているということでした。
社会の側に配慮や工夫があれば、障害は取り除くことができる——まさにこれが「社会モデル」の視点だと実感しました。
この考え方に基づき、本ブログでも「障がい」ではなく「障害」という表記を用いています。
第4章:申込後に参加して実感!体験会がもたらす3つの“確かな価値”
体験を終えて最も強く感じたのは、「申し込んだ後であっても、体験会に参加して本当に良かった」という確信でした。
その理由を、ここで3つにまとめてお伝えします。
① テキストの理解が一気に深まる 実際に手引き介助を体験したことで、テキストに書かれていた一つひとつの手順が、どんな意味を持つのか、なぜ必要なのか、肌感覚で理解できました。これからの自宅学習が、きっと何倍も有意義になると確信しています。
② 資格取得後の未来が“現実”として描けた 第1回目で書いた「家族への安心感」「心の安定と自信」「社会とのつながり」——それらが、夢や理想ではなく、“手が届く目標”として明確になった気がします。
特に心に残ったのが、講師のこの言葉でした:
「困っている方を見かけたときに、ためらわずに手を差し伸べられる心を持っていてください。障害は、その人の一部でしかありません。大切なのは、一人の人間として対等に向き合うことです。」
③ 申込者でも“特典”対象と分かり、安心できた 第2回目でも触れた体験会参加者特典(合格後のバッジプレゼント)。申込書の備考欄に書いたものの本当に対象になるのか不安でしたが、「申込後でももちろん対象です」と直接聞けて、安心感が一気に増しました。

画像出典:公益財団法人日本ケアフィット共育機構
講師の「障害がある方も、障害を除けば同じ一人の人間。だから、必ず相手の意思を確認してください。上から目線で接する必要はない」という言葉も、心に深く残っています。
さらに、手話だけに限らず、気持ちを伝える手段は人それぞれ。言葉が通じなくても、心は通じる——そんな希望も、この体験を通して感じることができました。
やはり、「体験すること」には代えがたい価値がある。 学びの深さ、視点の変化、そして心の動き。 それらすべてが凝縮された、忘れられない一日となりました。
エピローグ:次は学習編へ ― 自宅学習から課題提出までサービス介助士の世界へ一歩踏み出す
体験会を終えた今、私はようやくスタート地点に立ったのだと実感しています。 講座への申し込みという“決意”だけでは見えなかった景色が、この短い1時間の体験を通して、まるで色を帯びたように感じられたのです。
「相手の立場に立って考える」ことの大切さ。 「手を差し伸べたい」という気持ちだけでは、届かないことがあるという現実。
そして何より、「学ぶことは、誰かのためになるだけでなく、自分自身を癒す時間でもある」—— そんな温かな気づきが、心の中に芽生えました。
これから始まる自宅学習や課題提出は、決して楽な道のりではないかもしれません。 けれど今は、不安よりも「学びたい」という気持ちの方がずっと大きくなっています。
体験会で得たリアルな学びを胸に、次は学習編へと歩みを進めていきます。 この一歩が、私の人生を少しでも優しく、そして豊かにしてくれることを願って。体験会を終えた今、私はようやくスタート地点に立ったのだと実感しています。
最後に…一緒に「サービス介助士」を目指しませんか?(PR)
この記事を読んで、「私もサービス介助士に挑戦してみたい!」と少しでも感じてくださった方がいらっしゃれば、これほど嬉しいことはありません。

※当リンクはアフィリエイトプログラムに参加しています。詳細をご確認の上、お申し込みください。




コメント