📘この記事は連載シリーズ「介護者のための明日が少し楽になるヒント(資格取得編)」の一部です
▶ 第1回:在宅介護の私が「サービス介助士」に挑戦! ― 動機編
▶ 第2回:ついに申込!資料だけじゃ分からなかったリアル ― 申込編
▶ 第3回:申込後でも体験会へ参加して大正解! ― 体験会編
▶ 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編
▶ 第5回:知識が“本物のスキル”に変わった瞬間 ― 実技教習・検定試験編(前編:1日目)
▶ 第6回(この記事):視覚障害者の手引きとロールプレイ ― 実技教習・検定試験編(後編:2日目)
▶ 第7回:資格取得後に生きる力に変わった「支える」という視点 ― 総括編
プロローグ:基本から学ぶことの重要性を知った初日から、さらなる挑戦へ
前編(1日目)では、高齢者疑似体験と車いす介助を通じて、「社会のバリア」と「合理的配慮」を体感しました。
2日目は、さらに高度なコミュニケーション力と判断力が問われる一日です。
視覚障害者の手引き誘導、グループでのロールプレイ、そして検定試験。まさに、知識が“本物のスキル”に変わる集大成でした。
第1章:2日目の講義とアドバイザーの声 ― 多様な障害への理解を深める
2日目の講義は、まず前日の「聴覚障害者の理解と接遇」の復習から始まりました。
続いて取り上げられたのは、知的・発達・精神障害者、そして視覚障害者への理解と接遇です。
これらの障害は外見だけではわかりにくく、同じ障害名であっても一人ひとりの状況は大きく異なります。だからこそ、マニュアル的な対応ではなく、その人の状態に合わせた柔軟な姿勢が求められることを再確認しました。
さらに、この日は視覚障害のあるサービス介助士アドバイザーの方から、日常生活での体験を伺うことができました。徐々に視力を失う過程で、情報の得方や生活の工夫をどう変えてきたか――教科書には載らない“生の声”に触れることで、机上の知識が現実の生活と結びついていきました。
法制度の整備やユニバーサルデザインの普及によって社会は少しずつ変わっています。それでもまだ、障害についての「理解不足」や「思い込み」が壁になる場面があることも事実です。今回の講義は、そうした壁を少しずつ取り払うために必要な視点を与えてくれたと感じました、障害者差別解消法などの法整備がすすみ、社会的バリアが少なくなる社会に向かっていることを実感しました。
第2章:視覚障害者の手引き誘導 ― 「目を貸す」という役割
2日目の最初の実技教習は「手引き誘導」です。ペアを組み、交互に視覚障害者役と介助者役を体験しました。
視覚障害者役を体験会の手引誘導の教習のときに体験したときは、目をつぶっただけでした。アイマスクを装着すると、世界は一瞬で闇に閉ざされます。最初に感じるのは、不安と緊張。そしてそのとき頼りになるのは、介助者の声と肘を通じて伝わる微かな合図だけでした。
一方、介助者の立場ではどのようにコミュニケーションをとって、手引をすればよいのか。ここで講師が強調されたのは、「介助者は“代わりに判断する存在”ではない」ということ。
介助者の役割は、相手に“正確な情報を伝える”こと。つまり「目を貸す」ということです。
- 「高さ10cmの上りの段差が2段あります」
- 「幅1メートル、長さ2メートルの通路を通ります」
- 「椅子の背もたれは丸く、右側にひじ掛けがあります」
ただ「段差があります」ではなく、具体的な数字や状況を伝えることで、最終的にどう動くかを決めるのは視覚障害のある本人です。
これは「ノーマライゼーション」の基本的考え方にも通じています。
視覚に障害があっても、視覚障害者は私たちと同じように自分で状況を把握し、判断し、行動する力を持っています。手引きをする人は、そのプロセスをサポートする「情報の通訳」であり、決して“代行者”ではありません。
この意識を持つことで、障害者を「助ける対象」としてではなく「障害を共に受容し、共に生きる」人間として尊重する――そのことを強く学びました。
第3章:ロールプレイ ― 即興の現場で問われた判断力
午後は「車いす操作」、「手引誘導」の実技チェックから始まりました、実技の順番が最初だったので、声がけをすることから忘れてしまい、ティッピングレバーの操作も完璧ではありませんでしたが、受講生の声かけと講師のアドバイスもあり、なんとか無事に終えることができました。
その次の実習が小グループに分かれたロールプレイです。サービス介助士として、介助される立場になって、どのような介助をしてもらったら安全で安心できるかを考えるのがポイントです。
私のチームに与えられたテーマは「ショッピングセンターで、発達障害のあるお客様に商品を販売する」というもの。
大まかなストーリーと、登場人物の背景を与えられ、打ち合わせも最小限のまま即興で挑みました。もちろん正解はありません。大事なのは困っている人に対して「その場でどう判断して動くか」です。
他のチームも、視覚障害者、聴覚障害者そして車椅子使用者への接遇を行うリアルなシーンを演じました。それらを見て、困っている人は高齢者や障害者だけでなく、健常者でも困る場面があると今更ながら気づきました。困っている人に声をかけて、無理のない範囲で自然に手伝えることがホスピタリティ・マインドを持つサービス介助士なのだと実感しました。
演技を見守る講師や参加者からの演技後のフィードバックは実践的で、学びが深まりました。
「声のトーンがやさしくて安心感があった」「もう少し周囲の状況を説明すると良かった」
そうした指摘も、ロールプレイの個別の評価ではなく「一緒に考える」ためのもの。会場には温かい一体感が流れていました。
ロールプレイが終了し、講師から2日間の実技教習のまとめの講話がありました。
とても有意義な2日間を過ごすことができました。その思いを込めて各自が明日からの行動宣言を発表しました。このあとの検定試験は途中退席可能なので、このタイミングで締めくくりです。
全員で挨拶をして実技教習は終了しました。
第4章:検定試験 ― 学びを振り返り、自信に変える時間
2日間の締めくくりの検定試験は、マークシート方式で、50問中70%以上の正解で合格です。
初日に講師から聞いた「15問も間違えても大丈夫ですよ」という言葉が心の支えになりました。
検定試験は単に点数を取るための試験ではなく、「これまでを振り返る機会」としての意味合いが強いので、高得点を狙う必要はありません。「2日間の学びを振り返り、自信に変える時間」なのです。
合格するための最大のポイントは、第4回の学習編でも触れましたが、「正しいもの」を選ぶのか「正しくないもの」を選ぶのか、問題文の意図を見誤らないことです。
試験時間は50分です。多くの受講生の方が途中で退席されました。私も割と早くに記入は終了しましたが、試験問題を見つめながら、この2日間を振り返って最後まで席を立ちませんでした。
エピローグ:資格はゴールではなく、相手を想う“旅の始まり”
2日間の実技教習を終えて私が感じたのは、「相手を障害者としてではなく、一人の人間として尊重する」というシンプルで当たり前の視点でした。
知識として覚えていたことが、体験を通じて「血の通った知恵」に変わったとき、私は強く思いました。――これは試験に合格するための学びではなく、これからの人生を豊かにする学びなのだと。
サービス介助士の資格は、取得して終わりではありません。そこからが本当のスタートです。家族を介助するとき、地域で困っている人を見かけたとき、あるいは仕事の現場でお客様と接するとき。どんな場面でも、学んだ姿勢とスキルは必ず活かせます。
もしこの記事を読んで、少しでも「自分も挑戦してみたい」と思ったなら――それが、あなたの第一歩です。
机上の知識を体験に変え、自分の成長に変え、そして誰かの安心や笑顔につなげていきませんか?
合格証書が届いたら、この連載の「総括編」で学び全体を振り返り、これから挑戦される方へのヒントを整理してお届けします。あなたがその一人になってくださることを、心から願っています。
関連記事リンク
- 第3回:申込後に体験会へ参加して大正解! ― 体験会編
- 第4回:学習スタート!テキスト攻略&自宅学習から課題提出まで ― 学習編
- 第5回:知識が“本物のスキル”に変わった瞬間 ― 実技教習・検定試験編(前編:1日目)
最後に…あなたも「サービス介助士」を目指しませんか?
この記事を読んで、「私もサービス介助士に挑戦してみたい!」と少しでも感じてくださった方がいらっしゃれば、これほど嬉しいことはありません。

※当リンクはアフィリエイトプログラムに参加しています


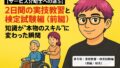

コメント